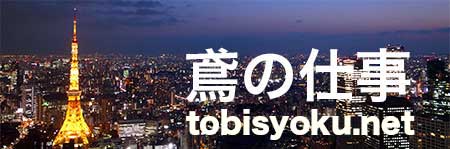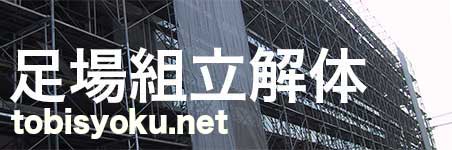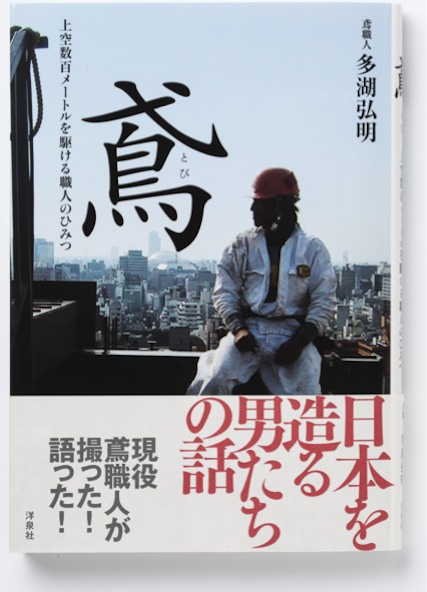高層ビル建築には絶対不可欠な存在、鳶職人とタワークレーン
高層建築現場の一番上にそびえ立つタワークレーン。
それは高層化されている今の
日本の高層建築には、絶対不可欠な存在である。
しかし、タワークレーンがどのようにして、工事現場のてっぺんにあるのかは一般的には謎とされている。
ここでは建設中のビルのてっぺんにあるタワークレーンの謎について解決していこう。
最大吊り上げ能力70tの大型から、1tの小型のクレーンまで、種類は実に様々。
ここでは、主に高層建築現場で使用されている、
大型タワークレーンを中心に話を進めたいと思う。

タワークレーンの組立、解体作業。これも鳶職人の仕事である
正式名称はクライミングクレーンと言い、
その名の通り、自身の力で上に登っていくところから、
「ビルを駆け上がる=クライミング」と名付けられた。
機体は細かく分割された部材によって構成されており、
現場で、組立、クライミング、解体していく。

|

|

|
この一連の作業、主に鳶職人がこなすのだが、
実は一般にはあまり知られていない
タワークレーン専門の特殊部隊が存在する。その名も、
タワークレーン技術指導員。
彼らの主な仕事はクレーンの組立、解体、クライミングの指導。
それだけではなく、機械の調整、修理、点検等も行う。
更にはクレーン運転士に機械の説明や運転方法の指導も。
タワークレーンに関する事はどんなことでもこなし、
絶対にミスは許されない立場におかれている。
気性の荒い鳶職人達を指導する立場、
生半可な知識と技術では、逆に指導されてしまうことになりかねない。
作業技術や知識はもちろんのこと、
指導員としての腕や人間性も問われるのだ。
機体はデリケートな為、組立解体の順序が細かく決められている。
その為、鳶職人は指導員からの手順や指導、助言を元に作業を進めていくのである。
sponsored Link
タワークレーン組立手順
では、どのように組立てられて、解体されていくのか。
組立ての手順は
まず、ベース架台をセット、その上にマスト(柱)を乗せ、本体をセットする。
 |
 |
 |
 |
それから本体に、ジブ(クレーンの腕)を取り付け、
起伏、巻き上げ下げ用のワイヤーを通します。
 |
 |

組上がった後に、クライミング、
そして監督署の落成検査を受けていよいよ稼働となります。
 |
 |
クライミングとは?
クライミングとはクレーン本体がマストを昇ることを言い、
下降する時は、「逆クライミング」と言われる。
大型クレーンでは油圧シリンダを用いたクライミング方式が主流で
油圧昇降シリンダの伸縮運動によってクレーン本体が
マストを昇降する事が可能となる。
昇降シリンダ(画像中央)には、
上部と下部にカンヌキが設置されている(画像右)

|

|

|
油圧昇降シリンダーの働きと原理
まず、下部のカンヌキをセットし、油圧シリンダを伸ばして、
クレーン本体ごと持ち上げていき、規定の高さで上部のカンヌキをセットする。
上部のカンヌキでクレーンを支えたら、下部のカンヌキをたたみ、
伸びたシリンダーを縮めていく。
 |
 |
油圧シリンダーが縮みきったら、また、下部のカンヌキをセットし、
上部のカンヌキをたたんで、油圧シリンダーを伸ばしていく。
このようにして、カンヌキで交互にクレーン本体を支え
シリンダーの伸縮を繰り返すことで、
クレーン本体を昇降させることができるのだ。
その他のクライミング方式
油圧昇降シリンダー他にもクライミング方式があり、
小型のクライミングクレーンで用いられているのが、
電動チェーンブロック、ワイヤロープなどのクライミング方式である。
電動チェーンブロックでのクライミングでは、
マストの最頂部に取り付けた電動チェーンブロックで、
クレーン本体をつりあげてクライミングしていきます。
このようにして組み立てられたクレーンは、
建物と共に空へ向かってどんどん上がって行くわけですが、
建物と同じようにクレーンも上げなければなりません。
このクライミングには2種類の方法があり クレーンを建物の内部に建てるか、外部に建てるかで変わってきます。
タワークレーンクライミング方法
フロアクライミング
フロアクライミングは建物の本体鉄骨を利用して、クライミングし、
最上段にクレーンのベース架台を乗せ替えることを表している。
建物の内部にクレーンを組み立てている時に用いる方法である。
ではどうやって乗せ変えてるか?だが、 絵と写真を参考に説明しよう。
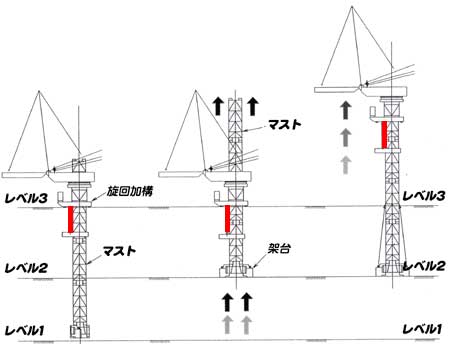
クレーン本体部分を逆クライミング(下降)させ、
上画像のレベル3の位置に施工された受け架台に機体を預け、固定する。
固定したらレベル1部分に設置していたベース架台のアウトリガを縮める。
 |
 |
そしてクライミング開始。
本来は、油圧昇降シリンダーを用いてクレーン本体を昇降せさていく。
(油圧シリンダーは画像の赤い部分)
しかし、今回の場合、クレーン本体がレベル3の受け架台に固定されているため
クライミングすることによって、マストの方が上がっていきます。
マストが上昇するとともに、ベース架台も持ち上がっていきます。

|

|

|
ベース架台がレベル2の受け架台まで上がったら、
アウトリガを伸ばしベース架台を固定します。
ベース架台を固定したら再びクライミング。
今度はクレーン本体がマストを上昇していきます。
 |
 |
この一連の作業のことをフロアクライミングと言い、
定期的に繰り返すことでクレーン本体は建物と共に、
高く高く空に向かい上がっていくのです。
マストクライミング
こちらは建物の外部にクレーンを組み立てている時に用いる。
ベース架台はそのままで、マストを継ぎ足し、
クライミングしていく工法。
ただし、この工法だと建築するビルの高さに見合うだけの
マストの数が必要になるため、規定の高さ毎に補強を入れなければなりません。

|

|

|
解体時も地上まで逆クライミングしてから解体する為に、
ヤードの確保も必要となります。
マストコラムクライミング
建物の本節鉄骨柱をクレーンのマストにして立てていく工法。
この工法、フロアクライミング工法と比べて、
何処にメリットがあるのかと言うと、
ダメ穴、つまりクレーン周りの開口をなくすことができる。
 |
 |
 |
開口部をなくすことによって最上階の穴がふさがるので、
下の階が、天候に左右されることが少なくなり、
早い段階で仕上げ工事に着手することができる。
 |
 |
更には、一般のタワークレーンのベース架台、マストが不要な為、
組立解体の工期を短縮することができる。
sponsored Link
タワークレーン解体方法
続いて解体方法と手順。
あの高いビルのてっぺんまであがったタワークレーン。
どうやって解体しているのか?

複数のクレーンが設置されている場合は、
最後の一台になるまで隣り合ったクレーンで解体していきます。
残った最後の一台のクレーンAで一回り小さなクレーンBを組み立てます。
そのクレーンBでクレーンAを解体。
そして更に半分の大きさのクレーンCを組んでクレーンBを解体します。
 |
 |
このように組み替え組み替えを繰り返し、クレーンのサイズを小さくしていくのです。
そして一番最後には人力や本設の点検用ゴンドラを利用して解体。
最後のクレーンは解体すると一つの部材が80kg未満になります。
これを本設エレベータ、点検用ゴンドラなどで降ろします。
 |
 |

 |
 |
 |
 |
 |
コレはあくまでも一例であってその現場に応じて変化します。
今ほど機械が発達してない時代では、丸太で三脚デリックを組み、
ウインチ(巻き上げ機)と滑車を応用して解体、
運搬の際にはころ引きなどを利用していた。
現在においても、接合部のボルトなどは
径が大きいために、打撃メガネレンチ等を用いて、
鳶職たちがハンマーで叩いて施工している。
 |
 |
いつの時代でも、最後は人の手で解体、 搬出されるのに変わりはない。

sponsored Link